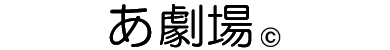【あ劇場©】へようこそ。
本日の晩婚パパの育児実録の演目は【ごっこ遊び好きは何歳まで続く?小3・一人っ子の想像力の発達効果より】です。
我が家の小学3年生の子どもの「あおば」は、ごっこ遊びが本当に大好きです。
一人っ子なので日常的な遊び相手が主に大人の親であることもあってか、ごっこ遊びで自分の想像の世界にどっぷりと浸れることもあるのだと思います。
そのおかげで、創造的な想像力が発達してくれている効果・メリットをスゴク感じています。
そしてその効果をとても感じているからこそ、次のように思うのです。
その心は、「まだまだ続いて欲しい!」から。
実際に付き合うのは結構大変な時もありますけどね(笑)。
具体的な「効果・メリット」としては、以下の例などが挙げられます。
《本ページはプロモーションが含まれています》 【あ劇場】へようこそ。 本日の育児実録の演題は【全国統一小学生テストのメリット!都道府県別の成績優秀者の賞状&額縁もあり!】です。 当記事では、 全国統一小学生テストのメリ[…]
このような実例から(賞状いただきました)、「ごっこ遊び好きの子の将来は明るい!」と感じています。
詳しくは、本文をご覧ください!
ごっこ遊びは何歳まで&いつまで続く?通説と近年の状況
近年、子どものごっこ遊びをする年齢の短期化が懸念されているそうです。
なぜ懸念されているのか?
後述の学術論文でもふれている点になりますが、それはもちろん、ごっこ遊びに数々のメリット、子どもの発達に重要な役割を果たす効果があるからです。
ということは、ごっこ遊び年齢の短期化というのは、そのメリット・効果を得る機会の「損失」を意味することになります。
これまでの通説は、1~2歳の頃から『見立て遊び・つもり遊び』の段階が始まり、4~5歳の時点で『ごっこ遊び』がピークを迎える。そして小学校の3~4年生ぐらいまで続く、というものでした。
短期化とは、「5歳ぐらいで終わってしまう‥‥」ということ。
小3~小4=9~10歳頃まで続くのが一般的であったとすれば、5歳というのはその半分のみの期間。
そのことが懸念されているのは当然だと感じます。
逆にいえば、ごっこ遊びをする期間がより長ければ、そのメリット・効果を十分に得られる可能性が「高まる」ということに。
であれば、親として気にかけるべきことは、 以下になるかと。
ごっこ遊びを好きでいてくれる期間を「何歳まで伸ばせるか!」の気持ちでもって、どう導いていけばよいか?(=コーチングしていけばよいか)、と考えるべき。
と。
ごっこ遊び=幼児では「ない」小学生の発達にも効果大
《ごっこ遊びのピーク》は一般的に4~5歳の間。
そう考えられているので、「ごっこ遊びは=幼児期の遊び」という誤ったイメージが「ある」と思われます。
ですが、近年の様々な研究の成果からすると、そのイメージは間違えで「ある」といえます。
その点は、ごっこ遊びがもたらす効果・メリットの内容の一覧を確認すれば、あきらかです。
ごっこ遊びの効果・メリット
以下、《ごっこ遊びの効果・メリット》として挙げられている点となります。
- 観察力
- 表現力
- 想像力
- 計画性
- コミュニケーション能力
- 社会性(ルールを守る力)
- 協調性(譲り合いの気持ち)
- クリエイティブ能力(道具の手作りにより)
などなどですが、果ては「将来的なジェンダーギャップの解消」にもつながるとの見方まで。
上掲リストにある「効果・メリットの内容」を鑑みるに、これだけの内容を伴う《ごっこ遊び》が、“幼児期のみの遊び” であるはずはありえません。
というか、この内容からするとむしろ、「小学生」においてその効果がより花開くのではないか、とさえ感じられるのではないでしょうか。
なお、個人的には上掲リストの《ごっこ遊びの効果・メリット》の中に、もう1つ付け加えたい点があります。
追加したい点は、 こちら。
です。
今年(2022年)の6月にウチの子は初めて、大手進学塾の四谷大塚が主催する「全国統一小学生テスト」を受験してみました。
来月・11月3日に行われる「全国統一小学生テスト」はTVCMも流されているようですが、前回まではそのような大掛かりな宣伝はなかったと思います、多分?。
ですが、たまたまその情報を知ったママが本人に聞いてみたところ、
ということになり、ものの試しにということで受験をしてみたのです。
ウチの子は《大の本好き・読書好き》なので、なかなかの「読解力」を持っているだろうと予想はしていたのです。
ですが、所謂「学習塾」などには通っていないこともあるので、「そこそこよい得点が取れるといいな~」ぐらいに思っていました。
ところが蓋を開けてみると、「国語の偏差値が70台!」という予想は遥かに上回る好結果が出て驚いたのでした。
★前回の「全国統一小学生テスト」の結果については、当育児日記の こちらにも関連記事があります。
【あ劇場©】へようこそ。 本日,2021年06月20日の晩婚パパの育児日記の主な演目は【四谷大塚『全国統一小学生テスト』の結果診断レポート《君だけの診断レポート》】について。 本日は,先日(6/6・日)あおば(ウチの小3の子供)が受[…]
当初、その好結果の理由は、《大の本好き・読書好き》によるものだと考えていました。
ですが‥‥
と、ちょっと気になっていたのでした。
それで「ハタ」と気づいたのが、《ごっこ遊びの効果・メリット》。
《ごっこ遊び》が育む「想像力」というものは、「読解力」においても非常に重要な点です。
「読解力」においては、文法の理解や語彙の知識といった土台的な部分が欠かせないことは確かです。
ですが、それだけでは「ホンモノの高い読解力」は身につきません。
「ホンモノの高い読解力」には、主人公はどのような気持ちでいるのかや、著者がどのような意図でその内容を書いたのか、などなどの点に対する「高度な想像力」が必要となるからです。
そのような「高度な想像力」を身につけるためには、静的に想像力を働かす《本・読書》だけでなく、動的に五感も駆使して想像力を働かす《ごっこ遊び》の両輪が働くコトが必要なのではないかと思います。
《ごっこ遊び》が育む「想像力」は《本物の読解力》を育む「想像力」でもある。
(手前味噌ながら)ウチの子どもの普段の様子や「全国統一小学生テスト」の結果より、そのように感じるのでした。
ごっこ遊びが小学生の想像力などの発達にも効果的であることを示す学術論文
『ごっこ遊び 発達 小学生』と、Googleで複数ワードでの検索をしてみると、次の学術論文がヒットしましたので、紹介ならびに引用をします。
引用内容出典先:幼児のごっこ遊びの想像力について明神もと子 – 被引用数: 5(2021年10月21日現在)
なお、当該学術論文のタイトルは『幼児のごっこ遊びの想像力について』となっているのですが、実際の内容に関しては幼児期だけではなく小学生の時期についても幅広くふれています。
また、親や大人の向き合い方に対する提案にまでもふれている内容となっています。
以下、同記事の最後にまとめられた「全体的考察」部分からの引用内容となります。
~前略~ ごっこ遊びは子どもの創造的想像力の基盤であると考えられる。
ごっこ遊びは想像遊びともいわれ,幼児期がピークであるが,小学生ではより想像力が発達しているので,計画的な内容で,壮大な遊びが可能である。しかしながら,現代の子どもたちを取り巻く社会の変貌と文化状況の変化は子ども時代からごっこ遊びをなくしていると指摘されるようになった。テレビゲームなどの仮想現実の遊びが魅力的であること,学習など多忙であること,遊びを伝承する異年齢集団がなくなっていることと,大人がごっこ遊びを軽視して,関心を持たないことがその原因であろう。5歳の幼児でさえ,ごっこ遊びをしなくなったといわれる。いわんや,小学生はごっこ遊びを幼児の遊びとみなしているのであろう。子どもが遊ぶということが自明のことではなくなっている。大人が意識的に子どもの遊びを保障しなければならない。従来の研究は遊びの効用をあきらかにすることにあったが,これからは,遊びへの動機づけや大人の指導的役割などが課題になってくるであろう。
以下は、結びの段落になります。
IT技術の進歩によって,仮想現実の中に子どもがさらされる機会がふえていく今日,子どもの想像力とごっこ遊びの関係をとらえる意義があろう。
現在、「小学3年生」となっている子を持つ「親」としては、上掲の引用部分の中でも特に、以下の部分に注目させられたのでした。
~ 小学生ではより想像力が発達しているので,計画的な内容で,壮大な遊びが可能である。
~ 大人がごっこ遊びを軽視して,関心を持たないことがその原因であろう。
~ 従来の研究は遊びの効用をあきらかにすることにあったが,これからは,遊びへの動機づけや大人の指導的役割などが課題になってくるであろう。
そのとおりで、大人、中でも『親』の役割が非常に重要であると感じます。
ごっこ遊びが好きな子どもの将来は親次第?
その問いに対する答えは、以下のようになるのではないでしょうか。
と。
基本的に「ごっこ遊びが好きな子の将来は明るい」と言えるのは、先述の学術論文の内容にもあるように、「ごっこ遊びは想像遊び」ともいわれるからです。
この「ごっこ遊びは想像遊び」という点は、多くの専門家が認めている点です。
一例を紹介しますと、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授は、「ごっこ遊びは、場面やストーリーを自分のなかでつくり出す必要があるため、創造力が育まれる」と語っています。
ごっこ遊びは想像遊びであるので、その想像力により創造力が育まれる。
それはすなわち、自分の頭で考える力を自分で鍛える、ということになります。
この「自分の頭で考える力を自分で鍛える」というごっこ遊びが有するメリットは、IT技術・AI技術が飛躍的に発展するこれからの時代=子どもたちの将来に、とても重要な役割を果たすはずです。
その点については、教育学者で東京大学名誉教授の汐見稔幸さんも、「なにもない場所から遊びをつくり出す経験は、AI技術が発達していくこれからの時代に特に必要である」と話されています。
「これからの社会」には、ごっこ遊びのメリットが必要とされる。
その一方、「いまの社会」では、子どもたちがごっこ遊びから遠ざかってしまっている。
その現実と未来を考慮するとやはり、先でもふれたように、『親』の役割が非常に重要であると感じられます。
「ごっこ遊びは想像遊び」。そのことは、頭の中=脳内で「イメージを膨らませる・創り出す」という能力でもあります。
その「脳内イメージがもたらす可能性」については、以下の関連記事がオススメです。
《本ページはプロモーションが含まれています》 【あ劇場©】へようこそ。 本日の演題は【藤井聡太一家の幼児教育の具体例などに「理想の効果」や「大切なこと」を学ぶ】です。 幼児期・幼少期の子を持つ親であれば誰もが願うこと、それは「[…]
おわりに
本日もまた、子どもと一緒に《ごっこ遊び》をタップリしました。
最近のごっこ遊びのウチの子のマイブームは、「ポケモン」ネタ。
といっても、ポケモンのポケットモンスターの役を演じるのではなく、ポケモン同士のバトルの場面を演じるのでもありません。
ごっこ遊びの主な流れは、ポケモンの世界に登場する「登場人物」の役柄で “オリジナルのストーリーを作っていく” 展開です。
その意味では、《ごっこ遊び》から次の段階である《劇遊び》へと進む “途中段階” のようにも感じられるのでした。
本日は晩御飯前に身体も使っての「ごっこ遊び」をした後、晩御飯の食卓でも、ジャリボーイ&ガールズ(ポケモンの主人公の男の子とその友人たちのコト)が考える「ポケモンの新番組企画」の打ち合わせという設定での「ごっこ遊び」をしました。
その席でも、想像力の羽を大きく羽ばたかせて、何パターンものストーリーを紡ぎ出して楽しんでいました。
幸いなことに(?)、ウチの子の「ごっこ遊び」に対する好奇心・エネルギーはまだまだ当面、衰えることはなさそうです。
これからも“頑張って”一緒に遊ばないと。
子どものごっこ遊び好きが何歳まで続くのか?
楽しみにしていきたいと思います。
嬉しいことに、ウチの子は「小4」になってからも相変わらずの「ごっこ遊び好き」です。
おかげさまで(?)、小4となってからも「その良い効果」は継続中と感じています。
(※以下、その実績です)
《本ページはプロモーションが含まれています》 【あ劇場©】へようこそ。 本日の《コーチング的育児実録》の演題は【全国統一小学生テスト小4春秋「国語偏差値65以上」塾なし家庭の学習方法】です。 わが家の小学4年生の子どもは、小3[…]
《本ページはプロモーションが含まれています》 【あ劇場©】へようこそ。 本日の晩婚パパの《コーチング的育児実録》の演題は【社会なら全国統一小学生テストで100点満点が可能でした!】です。 先日(2022年6月末)、我が家の小学[…]
高学年となった「小5」となってからも、「ごっこ遊び好き」継続中です。
続編的な関連記事はこちらに 。
【あ劇場©】へようこそ。 今回の育児実録の演題は【不安?!小学校高学年でも続くごっこ遊びが導く将来像とは】です。 遠くない将来、子どもたちが大人になる頃には、社会は未知の「白紙」状態の未来を迎える。 それは確実な[…]