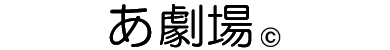【あ劇場©】へようこそ。
本日の《コーチング的育児実録》の演題は【小学生の都道府県の覚え方は「パズルゲームで五感を使う面白い勉強法」が効果抜群!】です。
本日は、わが家の小学3年生の子どもの「あおば」と一緒に、久しぶりに日本地図パズルでタイムトライアルゲームに挑戦しました。
タイムトライアルはほぼ半年ぶりでしたが、記録は前回とほぼ変わらずでしたので、小3ながらも 47各都道府県の形や日本地図全体の内での位置などの基本知識をシッカリと学習できていることが確認できました。
机に向かって勉強したわけでは「ない」にもかかわらず(嬉)。
プラス、その抜群の効果についてはこちらに 。
小学校低学年のうちからの積み重ねの成果が、といっても「楽しくゲームで遊んで」の積み重ねですが(笑)、以下のとても嬉しい成果につながりました 。
《本ページはプロモーションが含まれています》 【あ劇場©】へようこそ。 本日の晩婚パパの《コーチング的育児実録》の演題は【社会なら全国統一小学生テストで100点満点が可能でした!】です。 先日(2022年6月末)、我が家の小学[…]
都道府県の覚え方で日本地図パズルのゲームを薦める理由

まずは結論から。
47都道府県の覚え方で《日本地図パズル》をオススメする理由 は、以下になります。
「ゲームとして面白い」ことには、様々なメリットや根拠がありますので、以下その点を順を追って紹介していきます。
◆「ゲーム」で地理《都道府県》を学習できる3つのメリット
- 小学生の低学年のうちから遊びながら覚えられる点
- 47都道府県の位置関係や面積比を感覚的に掴める
- アナログのゲームだと触覚を利用できる
小学生の低学年のうちから遊びながら覚えられる点
この点はまさに「ゲーム」だからこそのメリットになります。
小学生も高学年になってくれば、机に腰を落ち着けて「暗記する」ということもできるようになってくるとは思います。
ですが、低学年やそれ以前の段階では「机に座って」というスタイルは、なかなか難しいのが一般的なところではないでしょうか。
その点を考慮すると「ゲーム」のメリットが十分に感じられるかと思います。
「ゲーム」の形式であれば、小学生の低学年のうちから「遊び」をつうじて学習・覚えることができます。
各都道府県の位置関係や面積比を感覚的につかめる
《日本地図パズル》の非常に大きなメリットは、この点にあります。
視覚的に見るだけでなく、「手で触れる」ことで、47都道府県の位置関係や面積比を感覚的につかめる点はパズルならではのメリットといえます。
ちなみにわが家では、この位置関係や面積比の感覚をシッカリと身体に染み込ませることを目的に定期的に「タイムトライアル」というゲーム性を活用しています。
パズルを「速く」完成させるためには、手に取ったピース=47都道府県が日本地図全体の中のどこに位置するかをシッカリと理解しておく必要があります。
また、面積比で大きな都道府県の岩手県や福島県からはめていくとパズルを組み上げていく速度を速めることができるので、面積比の感覚も自然に身に付きます。
ちなにみ、わが家の《日本地図パズル》は上掲画像にあるように北海道が十勝や釧路などの14の地域に区分されていて、パズル的にも地理学習的にも難易度が高いモノになっています。
おじいちゃんから頂いた “昔懐かし” のとっても昭和レトロな製品でしたので(苦笑)。
なお、わが家で使っている《日本地図パズル》は、残念ながらとうの昔に製造中止・・
ということで!
現在入手可能で「オススメ」な《日本地図パズル》といえばやはり、 こちら。
以下の約13分30秒ほどの動画では、昨秋(2022年・秋)に発売された「25周年スペシャルセット」を含め、アナログパズルならではのメリットを確認いただけます。
また、 こちらの約30秒ほどの動画では、上の動画ではふれていない特典物についての案内もあります。
アナログゲームだと触覚を利用できる
上の(2)の項目に関しては、例えばタブレットの地図パズルでも似たような形で遊ぶことが可能かもしれません。
ですが、デジタルなパズルだと「触覚」を活用することができません。
そうすると、都道府県同士の位置関係に関する部分や、面積比の感覚を記憶に定着させることがやや難しくなってくることが懸念されます。
一方、アナログゲームの場合は、その点がまさに利点で「手で触る」コトによって記憶の定着が図れます。
(この点に関しては、後の章でより詳しくふれています)
また、アナログである点は、上掲リストの(1)の点とも好相性で小学校の低学年より更に年齢が低い場合でも、アナログゲームなら問題なく楽しめるコトができるのではないでしょうか。
都道府県の理解が小学生を社会好きにするオススメ方法
小学生の子どもが「社会科」で学習する主な内容は以下の3つに分類できます。
- 地理(地図を含む)
- 歴史
- 社会全般について(時事問題を含む)
(1)地理に関しては、「小学生の社会科学習」だけでなく、中学・高校の段階になっても「社会科」に分類される全ての教科の「基本中の基本」となる部分です。
例えば、産業構造や人口の分布にせよ日本史にせよ、47都道府県の位置関係を理解しているといないとでは、その理解度に大きな違いが出てくる「肝」となる内容が《小学校の地理で学習する47各都道府県の地図の情報》であるのは間違いないところです。
(2)については、歴史を学ぶ上で「地理上の関係性を理解すること」がとても重要な点であるのは言わずもがなです。
例えば、甲斐の国(山梨県など)の当主である武田信玄が越後(新潟県など)の上杉謙信と何度も戦ったのは、互いの領土が接していたからでもあります。
その辺りの地理上の感覚は、現在の都道府県の位置関係を理解していないとつかみづらいところ。
歴史をシッカリ理解するのにも、地理の都道府県の知識は欠かせない点となります。
(3)の時事問題については、小学校中学年のうちは「道徳」の授業の延長線上にある面も色濃いかと思います。
その点を含め、小学生が社会科で学ぶ内容としては大切な点が多々あるとは思いますが、実際の学校のテストなどでは具体的な問題としては扱いにくい部分になってくるとは思います。
一方、中学受験が対象となると、「時事問題」は重要度が高くなるのは大きなポイント。
その際に、都道府県の地理的な位置関係による地政学的な説明が問われる問題が出題される可能性も高いかと思います。
こうしてみたとおり、 《都道府県の位置関係の知識》というのは、社会科学習の基盤をなすものと言って過言ではないかと思います。
《都道府県の位置関係の知識》が曖昧なままという状態は、算数でいえば「九九」が不確かな状態に近いぐらいかもしれません。
仮に「九九」でつまづいてしまったら、算数が好きになる可能性はゼロに近くなるでしょう。
だからこそ、「九九」を計算機まかせにせずに「暗記」しておくことは、今でも重要な学習方法なのでしょう。
同様に、小学生が「社会が好き」になるためには、その「肝」となる47都道府県の知識をシッカリと理解しておくことが欠かせないのでないかと思います。
プラス、当記事で紹介している「日本地図パズルを使ったゲーム形式の学習」は、小学生となる前の “幼稚園生の時点” から楽しむことが十分可能!
つまり、以下のような構図が成り立つのかと。
小学生になる頃には《47都道府県》に慣れ親しんでいる
得意意識を持つことにより小学校で社会が好きになる!
では、次の章では「幼稚園児」でも効果が見込めるであろう「五感を使う勉強法」を紹介します。
「面白い!」と感じ「五感を使う勉強法」その効果とは
小学生や幼稚園児の感受性はとても鋭敏で、「面白い!」と感じるコトはドンドン吸収をしていきます。
それは脳の機能的にも新しいコトをドンドン吸収できる能力が、非常に高い時期だからでもあります。
もちろん、大人でも「面白い!」と感じるコトであればドンドン吸収することができますが、その吸収力の高さに関しては「子どもには敵わない」というのが正直なところだと。
特に、キャラクターの類とかに対する子どもの記憶力って、ホントに驚きますよね(笑)。
その驚愕の記憶力の源となっているのは、次の2つの点だと思われます 。
- 面白い!と感じる気持ちの強さ
- 五感を総動員している点
脳には、「感情」に強く訴えることを「よく記憶する」特性があります。
(1)の点はまさに、その点を利用していることになります。
だからこそ、感情が素直でストレートな子どもは、「面白い!」と感じるコトをドンドン記憶していけるわけです。
(2)の点も脳科学的にはとても有名なトピック。
ただ単に、目で見るだけで覚えようとするより、手で書いたり声に出したりしたほうが記憶に残りやすい点は、誰もが実感を持って納得がいく点だと思います。
とかく大人は、記憶というと目で見て覚えるコトを連想しがちだと思いますが、子どもたちは実際に視覚だけでなく、聴覚や触覚を “多用して” モノを覚えていると思います(味覚とかは不明ですけど(笑))。
当記事でオススメしている《日本地図パズル》はまさに!「触覚」に訴えるので、その形状が記憶に「残りやすくなる」わけです。
そして、形が記憶に残るとその組み合わせ部分、パズルが「カチッ」とフィットした時のあのなんといえない快感的な感触もシッカリと記憶されることと思います。
ですので、青森県と秋田県と岩手県のこの箇所が「組み合わさるんだ」という感じで、47都道府県ごとの隣接する関係性までを自然と「記憶してしまえる」という仕組みになるわけです。
五感を使う勉強法の妥当性について
ではここで、「五感を使う勉強法」の妥当性についても確認を。
『五感を使う 勉強』と、Googleで複数ワードでの検索をしてみると、次のような 【強調スニペット】 での表示がされますので、引用します。
五感を使って暗記する
五感とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚です。 たとえば、ただ見て覚えるよりも声に出して覚えた方が覚えやすいですし、リズムにのせて覚えることも良いでしょう。 五感を刺激することで、記憶をより強固にすることができます。 複数の感覚器を同時に刺激することで暗記を効率よくすることができるのです。
引用内容出典先:大学受験の勉強で効率よく暗記ができる方法 – 代々木ゼミナール
この引用部分がある情報の情報源が「代々木ゼミナール」であり、その記事のタイトルが「大学受験の勉強で効率よく暗記ができる方法」であることを鑑みると、「五感を使う勉強法」の妥当性が高いコトは十分に確認できると思います。
しかしそう考えると、大学受験の勉強をしている高校生や浪人生より、幼稚園児や小学校の低学年の子どもたちのほうが、より効率的な学び方をしていると言えるのかもしれないですね、面白いモノです(笑)。
47都道府県の覚え方「パズルゲーム」活用の実践例
当記事では、小学生の都道府県の覚え方として「パズルゲーム」を使う勉強法をオススメしています。
という疑問が頭に浮かぶことと思いますので、実際にわが家で実践してきた事例を簡単に紹介しておきます。
以下、《日本地図パズル》を用いたゲーム形式の『タイムトライアル』の結果の推移になります。
| 年月日 | タイムトライアル結果 | 前回差 |
|---|---|---|
| 2020年月日不明 (初回) |
24~25分前後 | - |
| 2020年月日不明 (2~3回目) |
8分台 | -17分程 |
| 2020年12月6日 | 10分前後 | +2分程 |
| 2020年12月9日 | 6分10秒台 | -4分程 |
| 2021年5月上旬 | 6分台 | プラマイゼロ |
| 2021年5月19日 | 4分52秒 | -1分程 |
| 2021年11月07日 | 5分6秒 | +14秒 |
今回は約半年ぶりのタイムトライアルだったのですが、前回・前々回とあまり間隔を空けずに挑戦をした時と「ほぼ変わらない成績」をあげることができていました。
ということは、《47都道府県》の位置関係に関しての「記憶が既に完全に定着している」ということができるかと思います。
ちなみに、今回は3回タイムトライアルに挑戦をして、いずれも5分30秒を切る内容でした(5分6秒はベストタイム)。
なお、その昔、日本地図は得意分野であった大人の僕が挑戦しても、この日本地図パズルのベストタイムは4分40秒前後でした。
おわりに|抜群の効果実績とオススメの日本地図パズル
当記事では、小学生の都道府県の覚え方として「パズルゲーム」が効果抜群!とオススメしてきました。
わが家ではこの方法で小学2年生時より、子どもに遊びながら《都道府県》の知識を楽しみながら学ばせてきています。
その成果は、上掲のタイムトライアルゲームの結果表を確認してもらえれば一目瞭然かと。
本日の結果は、初めてタイムトライアルに挑戦した時の結果から約20分も短縮していましたので。
もちろん、本人も勉強をしているつまりなどはまるでなく、「面白いゲーム」の1つとして楽しんでいるからこその「この成果」なのだと感じます。
机にキチンと座ってお勉強するだけが学習ではないと思います。
わが家では「楽しく学ぶコトこそが1番身に付く方法」だと考えて、そうした環境を整えるコト(=コーチング)にこそ注力しています。
そして、その成果は「とてもいい形で出ています」ので、オススメです。
ですが、反省点も1つ。
それは今回のタイムトライアルが前回から間隔が空きすぎてしまっていた点です(苦笑)。
次回は感覚が鈍らないように間隔を空けずに、また一緒に挑戦しようと考えています。
【あ劇場©】へようこそ。 本日の育児実録の主な演目は【小学生の地理学習はゲームがオススメ!ドラえもん日本旅行ゲームと日本地図パズルで】です。 本日は、あおば(ウチの小3の子供)と久しぶりに、『どこでもドラえもん 日本旅行ゲーム5』で[…]
(※以下、後日「追記」した内容です)
さて、そのような感じで「積み重ね」を続けた成果は、想像以上に効果抜群!でした。
小学4年生となってから受けた『全国統一小学生テストの社会』ではなんと!「100点満点!」を取ることができました。
《本ページはプロモーションが含まれています》 【あ劇場©】へようこそ。 本日の晩婚パパの《コーチング的育児実録》の演題は【社会なら全国統一小学生テストで100点満点が可能でした!】です。 先日(2022年6月末)、我が家の小学[…]
この実体験があるからこそ!
小学生の都道府県の覚え方は「パズルゲーム」が効果抜群! と、オススメしています。